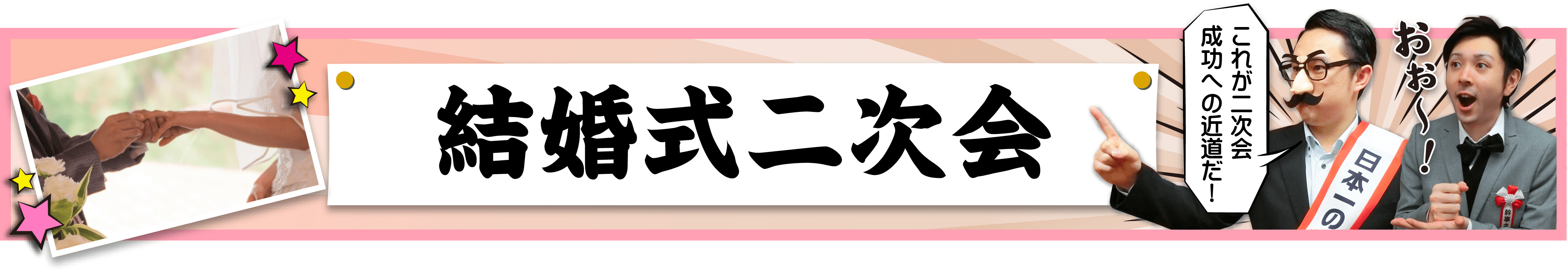結婚式二次会の宴席の食事形式で、重宝されているのがビュッフェ・スタイル。
「ビュッフェ」という言葉自体はもともと、フランス語での「buffet(飾り棚)」に由来するもので、テーブルに並べられた色とりどりの料理をゲストが自由に取り分けて席に戻る、「立食形式」の会食やパーティを意味します。
「食べ放題」なんて言われるとついフランクになりがちですが、社会人として、会社を代表する幹事さんとして、守っておきたいマナーがあります。
結婚式二次会を担当する幹事さんは、ビュッフェ形式のマナーを抑えつつ、ゲストを歓待したいですね♪
ゲストのみんなが楽しめて、お店にも迷惑が掛からないようにするために、ビュッフェ・スタイルの基本的なマナーをご紹介します!
いわゆる「バイキング形式」なのですが、この「バイキング」という言葉はじつは和製英語。
1950年代に帝国ホテルのコック長となった村上信夫氏が、当時流行っていたアメリカ映画「バイキング」(1958年)の豪快な食事シーンをヒントに、考案したレストランのサービス名だといわれています。
<<ビュッフェ・スタイルの基本的なマナー>>
◎コース料理と同様に前菜、メイン、デザートの順に料理を取っていく。
◎メインテーブルの料理を取り分けるときは時計回りに移動。
◎両手にお皿を持って会場を歩かない。
◎冷たい料理と温かい料理は混ざらないように別のお皿を使う。
◎ソースが混ざりそうな料理も別のお皿に分ける。
◎一度使った皿は再度使わず、新しいお皿に取り替えてから料理を取る。
◎責任を持って食べきれる量だけをお皿に取る。
◎仲間や先輩後輩、ゲストと、近い距離で会話を楽しむ。
コース料理ではないビュッフェ・スタイルの目的は参加者全員のコミュニケーションです!
結婚式二次会に参加したゲストが立食形式ならではの距離感でコミュニケーションを深められるようにするのが幹事さんのお仕事、「パネもく!」なら立食形式のビュッフェでも盛り上がること間違いなしです!
【二次会】結婚式のお土産選びのポイント

結婚式において一番の関心事と言えば、やはり新郎新婦の晴れ姿ですね!
しかし、ご祝儀や会費を考えると、引き出物などのお土産が気になるのが正直なところ・・・。
お土産も、大事な結婚式の印象を左右する大切な要素の一つです。
そこで今回は、新郎新婦・幹事さんがチェックしておきたい、お土産を選ぶ際のポイントをお伝えします!
結婚式の3種のお贈りもの
・引き出物→ご祝儀に対するお礼として、招待客に配られる贈呈品
・引き菓子→引き出物に添えて差し上げるお菓子。
・プチギフト→招待客が退場する際、新郎新婦が配る小さなお土産
引き出物とは、”馬を庭に引き出して贈った”という平安時代の慣習に由来され、やがて招待客へのお土産を指すようになりました。
主に、結婚式の招待客のご祝儀に対するお礼としてのギフトとして定着しています。
一般的には、披露宴の食事代の約3分の1ほどの価格設定で、品物を贈ります。
カタログギフトやブランドの食器類等が多いです。
引き菓子とは、引出物に添えて贈るお菓子です。
自宅に帰った後で、結婚式を振り返るきっかけ作りとして贈るため、招待客のご家族へのお土産という意味合いがあります。
価格の相場としては、1〜3千円ほど、紅白饅頭やバウムクーヘンなど、保存性の高いものが選ばれる事が多いです。
プチギフトとは、招待客が退場する時に、新郎新婦が一人ひとり手渡しする事が多いです。
送迎ギフトとも呼ばれます。
食品から雑貨まで、選ばれる商品は幅広く、クッキーやティーパック、ハブラシなどの日用品を贈るケースもあるようです。
手作りのものもOKで、新郎新婦の自由なアイディアで品物を選びます。
「3ない」がお土産選びのポイント!
1.かさばらない
2.重くない
3.残らない
引き出物や引き菓子、プチギフト選びのポイントは3つです。
〜かさばらない〜
遠方から来る招待客も多く、お酒が入った状態でかさばった荷物を抱えての帰宅は大変ですね。
〜重くない〜
こちらも帰宅時になるべく招待客の負担を避けるため、気軽に持って帰れるものを選びましょう。
安定した人気を誇るのが、カタログギフトです。
持ち帰りも楽で、招待客が品物を選べる点が支持を得ています!
〜残らない〜
食品や体験チケット、タオル・入浴剤などの日用品、お土産選びのコツの最後は、”残らないもの”です。
招待客の趣向と合わないものがずっと残ってしまうと、せっかくの贈り物も迷惑に繋がってしまうケースも・・・。
かさばらない・重くない・残らないの3点を意識して、結婚式・二次会などのイベントにふさわしいお土産を選び、イベントをより良く演出しましょう!
【二次会】失敗しないための、2つのポイント

結婚式二次会で失敗しないために!
成功例や失敗例など具体例を交えながら、ポイントを抑えておきましょう♪
新郎新婦の良い思い出となるように、気をつけるべき要所をお伝えします!!
内輪ネタのやりすぎは禁物
「内輪ネタは失敗する」というのは、結婚式二次会によくありがち。。
とは言え・・・新郎新婦が盛り上がるのも、家族やゲストとの思い出やエピソードです。
決して、内輪ネタはすべてNGという訳ではありません。
「タイミングや尺を考えてない、内輪ネタは失敗する」を念頭に置いて、プログラムの構成に気をつけましょう。
タイミングや尺など、どの程度にするかは、参加者の年齢層や、より親しいゲストの数などを参考にする事が良いでしょう。
使い方に気をつければ、内輪ネタは二次会の良いアクセントになってくれます。
お酒の取り扱いに注意
おめでたい席では、ついついお酒が進みがち。
しかし飲みすぎて失敗すると、せっかくの二次会も台無しになってしまうので、幹事さんにとってお酒の取り扱いは、注意が必要です。
お酒が得意ではないゲストや、妊娠されている方もいる事を想定して、お酒を出す際にはチェックしておきましょう。
お酒を煽るような事は絶対にタブーです。
【二次会】ゲームを考える上での心得
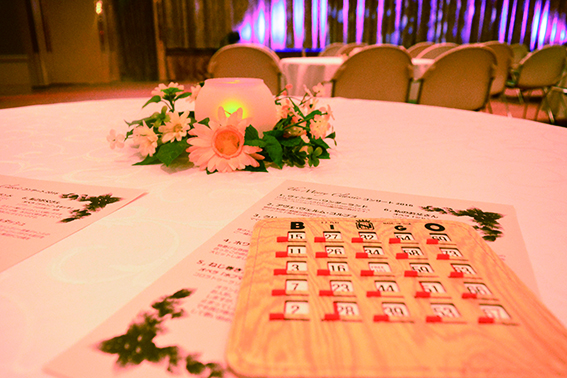
二次会で行うゲームの数や形式についておさらいしましたが、最後にゲームの選定や盛り上げるコツをお伝えいたします!
ゲームの企画や進行するにあたって、抑えておくと安心な心得をご紹介いたします♪
ゲームの選定は「見ているだけでも楽しめる」がポイント!
人数や予算、時間に限りがあるケースも多い二次会において、ゲスト全員がゲームに参加することが難しい場合があります。
そこでポイントとなるのが、「見ているだけでも楽しめるゲーム」の選定です。
参加者全体に呼びかけて楽しむのもコツのひとつではありますが、参加者の中には人前に出ることが苦手な方もいます。
無理にゲーム参加を強要してしまうと、会場の雰囲気が盛り下がってしまうので、事前にある程度参加者を決めておくと良いでしょう。
プロフィールなどを見ておき、新郎新婦のゲストの中で「盛り上げ役」のような、キーになる存在を探しておきましょう。
ゲームをやる前に相談しておくと、良いパフォーマンスをしてくれるかも!?
・可能であれば、全員が参加できるゲームを
・人前に出る事が苦手なゲストに、ゲーム参加を強要しない
・新郎新婦のゲストそれぞれの「盛り上げ役」のような存在を、事前に探しておく
景品やチーム戦などの工夫で、一体感を作って盛り上げよう!
二次会で一番盛り上がるシーンを作り出すゲーム、とは言えゲストの年齢層や会場のムードなど、やってみないと感覚がつかめないものですよね。
あらゆる状況においても、盛り上がる見せ場を作るのが幹事さんの腕の見せどころ。
例えば、新郎チーム・新婦チーム、テーブル毎での参加など、チームで争うスタイルにすると、全員参加が難しい場合でもゲームに一体感が生まれ、会場全体で楽しむ事ができます。
加えて、勝利したチームに景品を用意すると、さらにゲームが盛り上がる事でしょう。
豪華な景品はもちろん、少し笑えるような参加賞も準備して、ゲームの終わりに一花添えましょう。
・全員参加が難しい場合、チーム戦の工夫でゲームに一体感を出す
・勝利したチームには景品を出し、最後に盛り上がる見せ場を作る
結婚式の二次会は新郎新婦にとって、一生に一度の大事なイベント。
そのため、あらゆる準備に協力をしてくれる方も多いことでしょう。
当日は、みなさんの協力や景品での盛り上げを最大に生かして、思い出に残る二次会を成功させましょう!
【二次会】ジューンブライドの由来とは?

日本でもすっかりお馴染みの「ジューンブライド」。
結婚式といえば、6月というイメージを持つ幹事さんも多いのではないでしょうか?
そこで今回は、意外と知らない「ジューンブライド」の由来や、海外と日本での違いなど、豆知識をお伝えします♪
「ジューンブライド」の由来には、3つの説がある!
「ジューンブライド」を直訳すると、「6月の花嫁」June(6月)+Bride(花嫁)となり、6月に結婚した花嫁は幸せになるという言い伝えがあります。
「ジューンブライド」の由来について、ヨーロッパでは、3つの説があるとされています。
1. ローマ神話の女神JUNO説
6月を表すJUNEの語源は、ローマ神話の結婚生活の女神「JUNO」が語源です。
女神に見守られて6月に結婚をすれば、新婦は幸せになるという有力な説です。
2. 農家の繁忙期を避ける説
ヨーロッパにおいて、3〜5月は農業の繁忙期であり、その時期に結婚することはタブーとされている時代があったようです。
結婚が禁止とされていた3〜5月が明け、待ちに待った6月に挙式をあげる事が多く、6月は結婚の月という言い伝えです。
3. 良いお天気説
6月のヨーロッパは、日本と異なり、年間で最も雨が少なく、穏やかな気候になります。
花嫁がウェディングドレスを身に纏う特別な日ですから、天気の良い日が最も多い6月に結婚しようという説です。
日本での「ジューンブライド」の由来とは!?
その一方日本においては、とりわけ6月が結婚に適しているという理由はないように思えます。
ローマ神話の影響があるわけでもなく、結婚を禁止される時期でもなく、なんといっても6月は梅雨のシーズン・・・
ではなぜ、日本でも「ジューンブライド」という言葉が広まったのでしょう?
日本における「ジューンブライド」の始まりは1960年頃、某有名ホテルの宣伝がきっかけだという説があります。
6月は梅雨のシーズンで雨の日が多い上に、1960年頃当時の日本は整った空調設備が行き渡っていない時代でもありました。
天気が良くなく湿気で過ごしづらくなるため当然、結婚式を避けられる時期になります。
どうしても売り上げが落ちてしまう6月に、何か良い打開策はないかとホテルの従業員が見出したのが、ヨーロッパの「ジューンブライド」の風習だと言われています。
「ヨーロッパでは、ジューンブライドという風習があり、6月に結婚するとおしゃれな上に花嫁が幸福に!」というように大きく宣伝した結果、瞬く間に国内へ浸透しました。
ビジネス的な危機を回避する事がきっかけだった日本の「ジューンブライド」ですが、今となっては結婚に欠かせないワードとなりました。
空調などの環境も整えられ、会場は天候などに左右されにくくなり、多くの花嫁は6月に幸せの瞬間を迎える事となりました。
ジメジメとした空気を一掃するような幹事さんの仕事ぶりで、当日の祝福ムードをより一層盛り上げましょう!
【二次会】ゲームの形式
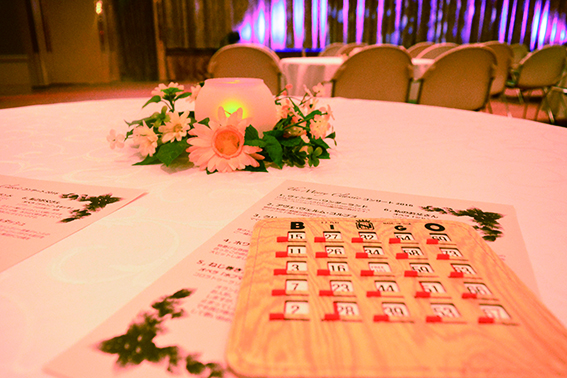
前回に引き続きゲームに関して、今回は行うゲームの形式についてご紹介します♪
大きく分けると、ゲームは3つの形式<個人戦><団体戦><代表戦>に分類されます!
個人戦!
ジャンケンまたはビンゴが個人戦の代表的なゲームで、1人が会場の全員と競う形式です。
利点:参加者が移動なくゲームができる。
欠点:淡々と進みやすいゲームが多く、盛り上がりに欠けてしまうケースも。
団体戦!
チームを分けて競う形式で、新郎新婦の馴れ初めに関するクイズなどが、代表的なゲームです。
利点:勝った時にチームで喜び合える分、盛り上がりやすい。
欠点:チーム分けの際に時間がかかってしまい、参加者の移動が必要。
代表戦!
参加者を特定のゲストに絞り、他の人はどの代表者が勝つかを予想する形式です。
利点:ゲームに参加するのが代表者のみの為、進行や管理が簡単。応援でゲームが白熱しやすい。
欠点:ゲームの参加者が少なくなってしまう。参加者の移動が必要。
それぞれのゲームの形式はメリット・デメリットがあります。
それぞれの特徴を把握し、時間や人数など状況に応じて、ゲームを選定しましょう♪
みなさまの二次会当日の成功を願っています^^
【二次会】ゲームの数

前回は余興の定番、映像上映についてポイントをご説明しましたが、今回も二次会において外せないイベント「ゲーム」についてです!会場の貸切時間を考慮すると、ゲームの数は1〜2つがベスト!多くても3つまでです。
1つのゲームに使える時間は20分前後が一般的!
二次会では、新郎新婦・ゲストと歓談する時間を設ける事が大事です。もし3つゲームを行い、計60分間の時間を使ってしまうと、歓談の時間や他の演出ができなくなってしまう可能性が出てしまいます。
ゲーム数を少なくして、1つ1つの景品の質を上げよう!
ゲームの数が増えると、それだけ景品の数を用意しなければなりません。決まった予算内で、景品の数を増やしてしまうと、景品1つ1つの単価が下がってしまい、盛り上がりに欠けてしまう可能性も・・・。二次会において「ゲーム」はメインイベントです!景品の質を上げて、参加者の意欲を最高に高めましょう♪
二次会における「ゲーム」は、数より質が大事!
間延びしない時間に抑えて、盛り上がる景品を用意し、二次会のメインイベントを華やかに締めくくりましょう!
みなさまの二次会当日の成功を願っています^^
【二次会】映像制作の注意点

余興の定番といえばやっぱり映像の上映!
ダンスや歌、お祝いのメッセージVTRなど、身内で用意するケースが増えてきました。
そこで今回は、映像作成にまつわる注意点をご紹介します♪
1.画面の大きさの比率は、4:3で作成!16:9はNG!
(16:9の場合、会場のモニターによっては、VTRの上下左右が途切れてしまう可能性がある。)
2.DVD-Rで用意する!
(ブルーレイのプレイヤーが用意されている会場は意外に少ないため。)
3.文字やテロップはセンター揃えにする!
(文字やテロップを端に寄せてしまうと、上映した際に文字が途切れてしまう可能性が出てしまう。)
4.映像のスタートから5秒くらいは、真っ暗画面で!
(黒い画面でストップしておけば、上映スタートの際にすぐに上映を開始できる。)
5.編集し終えたら、PC以外の環境(DVDプレイヤー)で再生テストをする!
(PCでは大丈夫でも、DVDプレイヤーでは再生できない可能性があるため。)
6.本番1週間前までには、実際の会場で上映テストを行う!
(会場の機器と焼いたディスクの相性次第では、再生できない可能性もあるため。)
7.接続ケーブルやケーブル差込口などよく確認する!
(パソコンとモニターを接続する際は、使用するケーブルなどを確認。特にMACは注意。)
8.当日は実際の会場で再生テストを!
(受付スタートまでに、当日の最終チェックを済ましておく。)
9.本番に間に合うよう、余裕のある作成スケジュールを!
(再生テストをするため、なるべく前倒して作成を進めておく。作成の際、拘りすぎにも要注意。)
10.その他・・・
・上映時間は7分以内が一般的!(長くても、間延びしないよう10分以内に収める。)
・内容は、新郎新婦・ゲストなど皆が楽しめる内容を!(一部の人だけ盛り上がるような内容は避ける。)
以上のポイントも抑えて制作すると、きっと当日は焦る事なく映像上映ができる事でしょう♪
ドキドキしながら本番を迎えてしまうと、せっかくの二次会が楽しめませんね・・・
ゆとりある制作スケジュールで、気持ちがこもった映像を上映し、みなさまの二次会当日の成功を願っています^^
【二次会】進行管理 その2

前回では、「進行管理」が二次会において、非常に大切な肝である事をご紹介しました(^ ^)
さて今回は、二次会で具体的に何をしたらいいんだろう・・?という幹事さんの疑問にお答えします♪
楽しい笑いあり、感動的な涙ありの一般的な進行プログラムをお伝えします!!
ビギナー君、二次会では具体的に何をするかもう決まっているかな?
実は、二次会自体にあまり行った事がなく、なかなか進行が想像しづらくて・・
そういう時は、まず標準的な二次会のプログラムを想定して、そこから自分なりにアレンジするといいだろう。
確かに、まず一般的なプログラムを知っておくと想像しやすいです!
標準的なプログラム
- 一、新郎新婦入場
- 二、新郎新婦の挨拶(ウェルカムスピーチ)
- 三、乾杯の音頭(新郎新婦ではなく、ゲストの代表者が一般的)
- 四、ケーキ入刀→ファーストバイト
- 五、歓談の時間(一回目)
- 六、プロフィール映像の上映
- 七、ゲーム(2つまでが一般的)
- 八、歓談の時間(二回目)
- 九、余興(無くてもOK)
- 十、サプライズ(新郎から新婦が一般的)
- 十一、新郎新婦キス(司会者からではなく、ゲストのコールからが一般的)
- 十二、新郎新婦から御礼のあいさつ
- 十三、新郎新婦退場
- 十四、送賓
以上が、標準的なプログラムです。
こちらの進行を雛形に、ぜひオリジナルのプログラムを作ってください♪
また、以下のポイントを意識して、プログラムを作成してみると良いでしょう。
- 貸切時間内に終わるよう、余裕を持った時間配分
- 歓談の時間はできるだけ多めに
- ゲームやムービーに偏りすぎず
- 内輪だけではなく、全体が盛り上がるように
以上のポイントも抑えつつ、新郎新婦がゲストみんなと話す機会ができ、楽しい笑いや感動の涙をいただけたら、それは完璧な二次会です♪
皆様の二次会の成功を心より願っています^^
【二次会】進行管理

二次会は、ゲストの受付に始まり、乾杯、ケーキ入刀、友人による余興、映像上映などイベントが盛りだくさん!
さらに、新郎新婦とゲストの歓談の時間も設けなくては・・・
そこで、大事になってくるのは「進行管理」です。
会場の貸切時間内でスマートに終わらせられるコツをお伝えします♪
ビギナー君、二次会を時間通りに進行するコツはズバリ2つ!なんだと思うかな??
ん〜臨機応変に対応する事と・・・
そのような感じで、果たして本番で臨機応変に対応できるかな?(笑)
時間通りに進行するには、「進行表」と「余裕」が大事なんだ。
事前にエクセルなどの表で、ゲスト受付〜退出までの項目を、ゆとりを持って貸切時間に割り振っていくんだ。
なるほど、事前の進行管理が大事なんですね!
ただし!1つ注意が必要なのは、進行項目を詰め込みすぎること。
ゲストの多くは、新郎新婦とゆっくり話すことも楽しみにしているから、余裕を持たせた進行管理で、しっかり歓談の時間も設けるんだ!
余裕を持たせた進行表を作成して、当日は思い出に残る楽しい二次会にします!!