
中締めと本締め(大締め)の違いってなんだろう?・・・という素朴なギモンも「幹事さんあるある」のひとつかも知れませんね。
会社の忘年会や新年会、謝恩会、結婚式二次会などでも、中締めが事実上の締めになっていたり、中締めと本締めをしっかり行ったり、と宴席によって締め方もさまざまです。
なにはともあれ「終わり良ければ全て良し!」。
締めのスタイルをしっかり知って、締め上手の幹事さんになりましょう♪
“中締め”という言葉を辞書で調べてみると「宴会などに一区切りを付け、手締めをすること」とあります。
一方、本締め(大締め)について辞書を引くと「ものごとの決着を祝って大勢で手を打つこと」とあります。
宴席が中締めだけで終わるケースもよくありますし、大規模な宴席の場合には中締め・本締め(大締め)を両方、行われることも多いです。
本締め(大締め)は中締めの後に退席が続いて、席が閑散として、座の空気が「もうそろそろ・・・」となったら頃合いでしょう。
どちらにしても締めは締めなので、一度やるか二度やるかは幹事さん次第!正式な決まり事ではありませんが、中締めは締めの予告、本締めが宴席の最後を、と考えるのが一般的となっています。
中締めは「退席したい人への配慮」「全員が揃っている中での宴会のけじめ」、本締めは「宴席の終了を告げるため」「有終の美を飾るため」が目的と考えると良いでしょう!
「締め」といっても、TPOに応じて締め方のバリエーションは豊富です。
中締めは三本締めや一丁締め、本締めでは三本締めなどで締めるのが一般的です。
また、関西では三本締め、関東では一本締め、一丁締めが多いようです。
どの手締めも発声する人が最初に「ヨウォーオ」と掛け声をかけて、みんなの息を合わせるのがポイント!最後に「ありがとうございました!」と、しっかりお礼の言葉で締めくくりましょう♪
ここではよく唱和される代表的な「締め」の種類をご紹介します。
・一本締め…
パパパン・パパパン・パパパン・パン と拍手を3・3・3・1で締めます。
・三本締め…
一本締めを3回繰り返すのが三本締めです。
パパパン・パパパン・パパパン・パン ×3
・一丁締め…
「ヨウォーオ」の発声と拍手1回で締めます。「関東一本締め」とも呼ばれる略式のもので、仲間うちの宴席で行われます。
「ヨウォーオ」・パン!
・大阪締め…
大阪を中心に伝わる締めです。「いおう(祝う)て」などの関西弁が特長的です。
「打ちましょ」・パンパン・「もひとつ」・パンパン・「いおうて三度」・パンパンパン
・一つ目上がり…
最初に人差し指だけで一本締め、次は中指を加えた2本で一本締め、今度は薬指を加えた3本、最後は正式な「一本締め」で計4回、行います。
(人差し指)パパパン・パパパン・パパパン・パン
(人差し指+中指)パパパン・パパパン・パパパン・パン
(人差し指+中指+薬指)パパパン・パパパン・パパパン・パン
(一本締め)パパパン・パパパン・パパパン・パン
・ヨヨヨイ…
大きな声を出すのがはばかられる会場で最適な締め方。小声で「ヨヨヨイ…」と発声しながら片手の親指と人差し指を打ちます。
「ヨヨヨイ・ヨヨヨイ・ヨヨヨイ・ヨイ」
・その他…
栄転や定年退職などの宴席で、応援の気持ちを込めて乾杯や万歳三唱で締めることもあります。
一本締めの「パパパン・パパパン・パパパン・パン」の最後の「パン」は拍手の数を9回から10回に合わせることで「九」に点が打たれて「丸」く納まる、という言霊(ことだま)が込められたものだそうです。関西では「来客」「主催者」「会場」の三者に対するお礼の気持ちから三本締めをします。
やっぱり最後は気持ちを込めて!
ただの儀礼ではなく、幹事さんはぜひ心を込めた手締めで「有終の美」を演出したいですね。

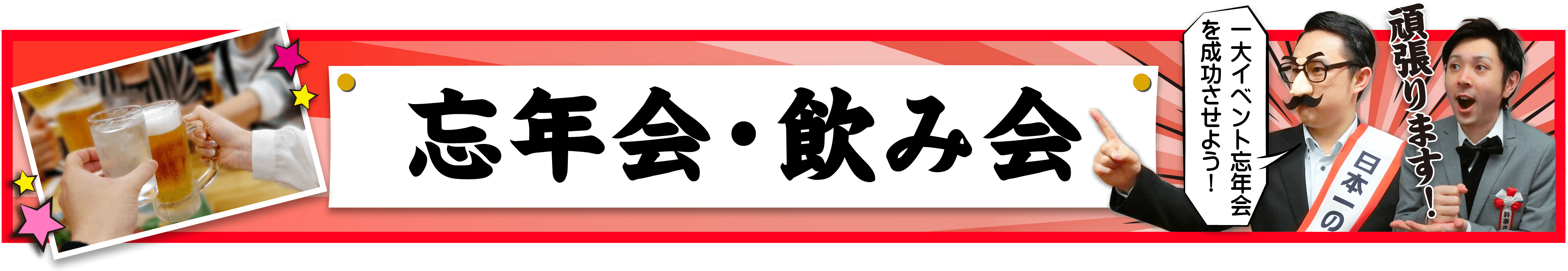
 忘年会開催の日程は12月下旬だとクリスマスと予定が重なってしまうこともあり、最近では中旬、下旬と早まる傾向にあります。年末がかき入れどきの業種の場合は11月に開催するケースも少なくありません。年末は会場もすぐ予約で埋まってしまうので、できるだけ早い会場選びが大切です。
忘年会開催の日程は12月下旬だとクリスマスと予定が重なってしまうこともあり、最近では中旬、下旬と早まる傾向にあります。年末がかき入れどきの業種の場合は11月に開催するケースも少なくありません。年末は会場もすぐ予約で埋まってしまうので、できるだけ早い会場選びが大切です。